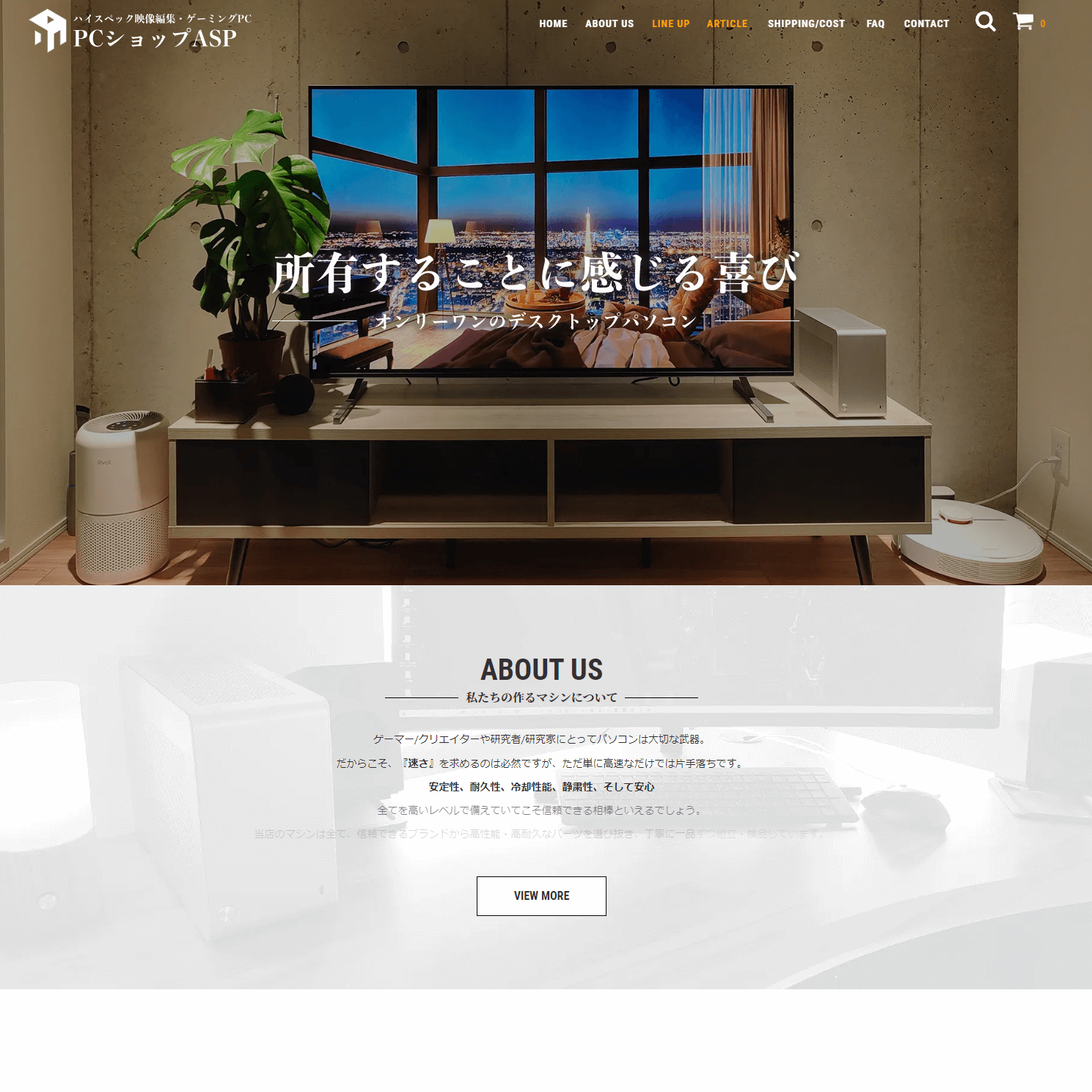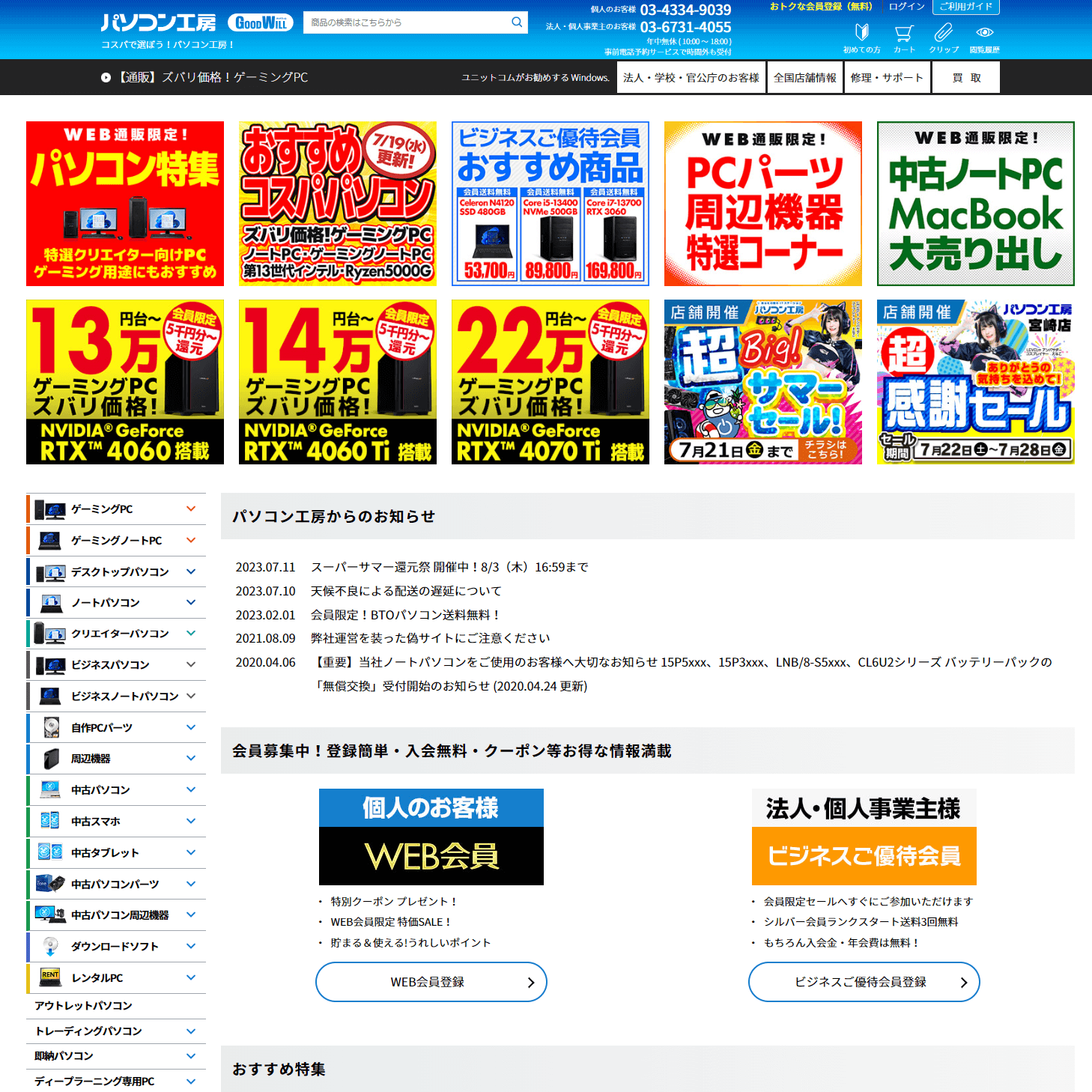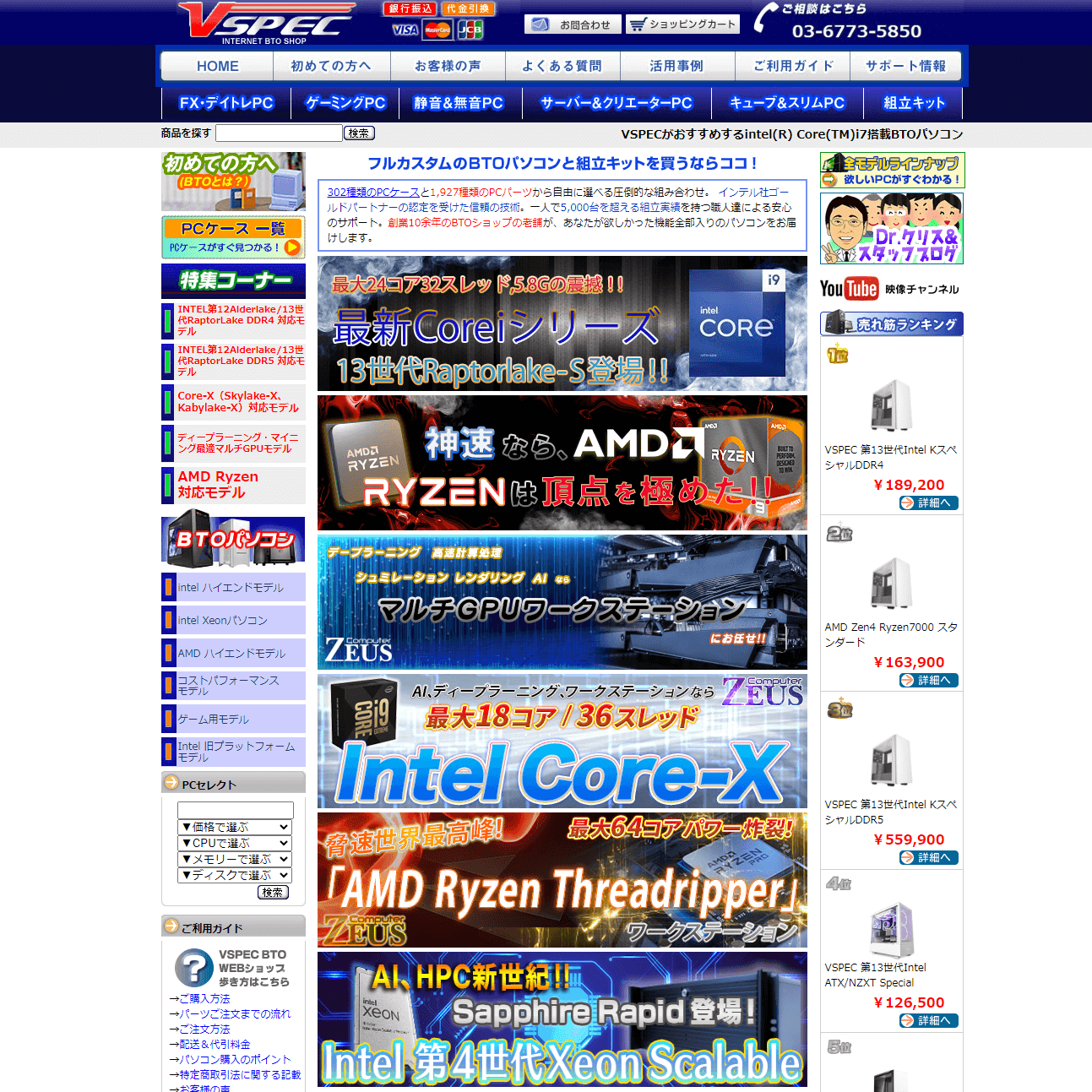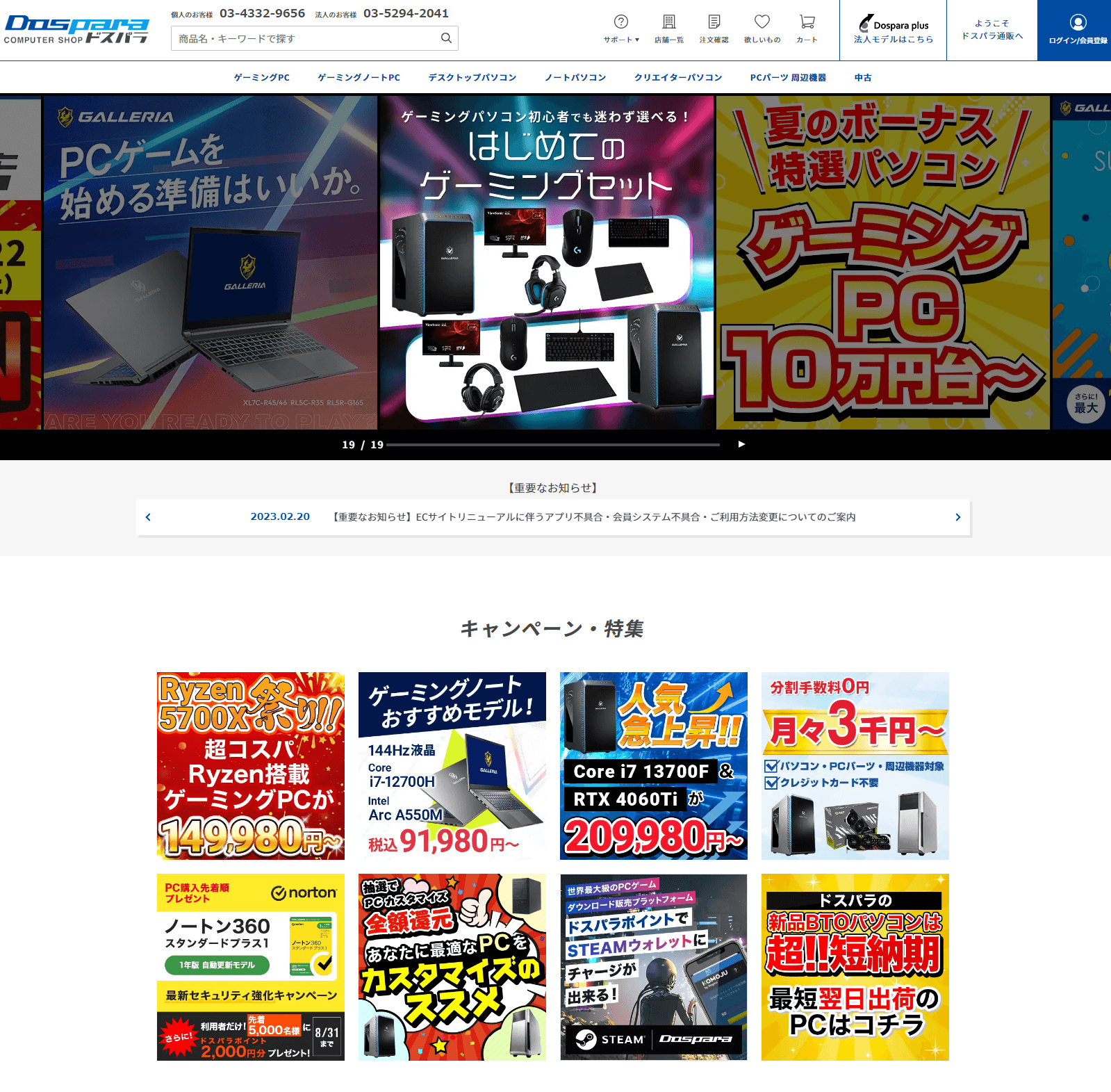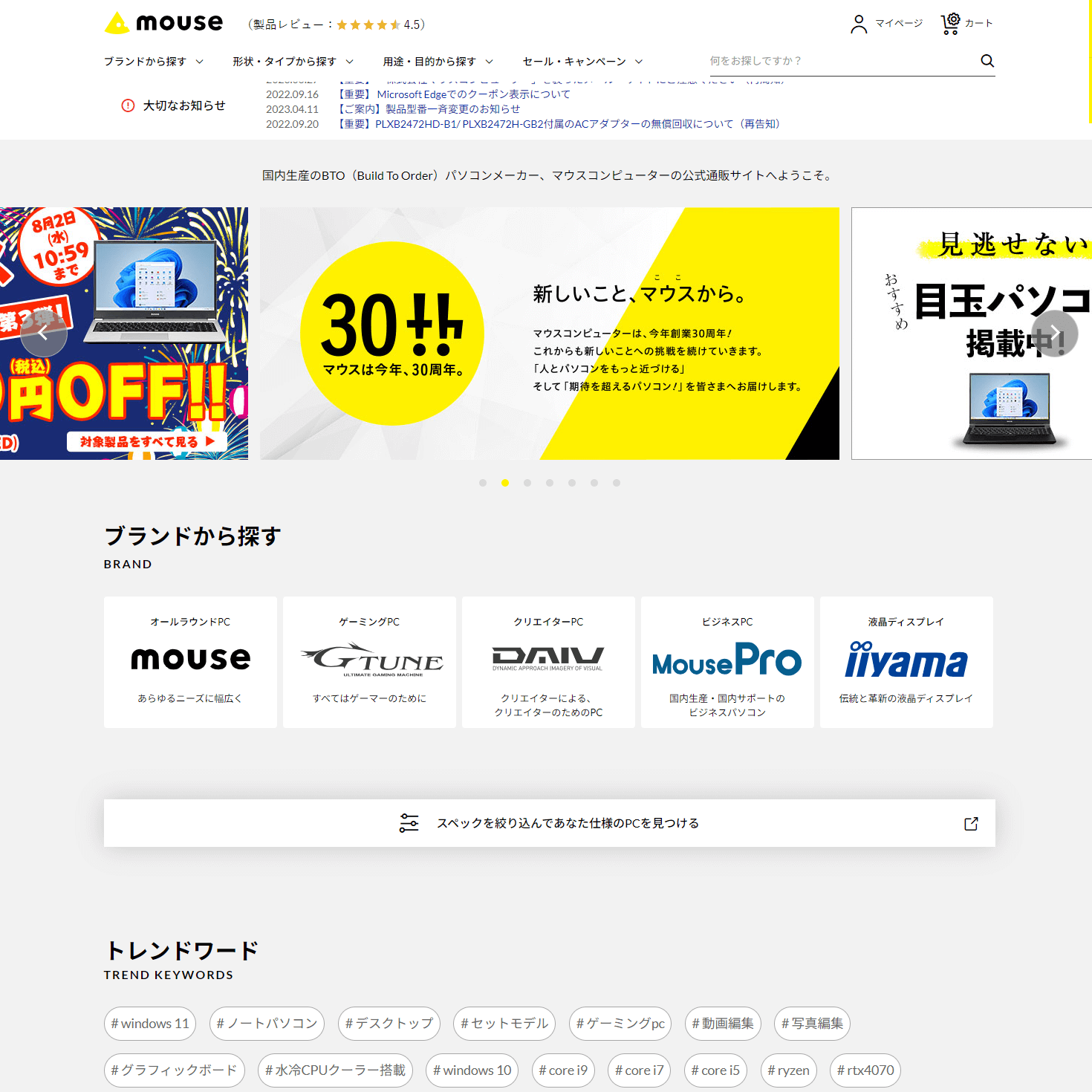自身が求めているようなパソコンは市販されていない、そんなふうに不満を感じている人もいるのではないでしょうか。より自身にぴったりのパソコンを手に入れたいのなら、BTOパソコンがおすすめです。BTOパソコンとはどのようなパソコンなのか、メリット・デメリットなども、わかりやすく解説します。
BTOパソコンとは?
BTOパソコンのBTOとは「Build To Order」を略したもの、すでに完成した状態で販売されているパソコンではなく、受注生産のパソコンです。
自身がこんなふうに使用したいという用途に合わせ、CPUやメモリ容量などを選ぶことができるので自由度が高く、しかもコスパに優れているという魅力もあります。
パソコンには種類があり、OSや形状で分類するほかに販売形態によっても分類することができ、BTOも販売形態の一種になります。販売形態によるパソコンの違いについて説明します。
メーカーが製造・販売するパソコン
パソコンの大手メーカーである、富士通、NEC、パナソニック、VAIOなどが製造し販売する構成済みのパソコンです。パーツを収めるケースである筐体をはじめ、キーボードなどすべてがメーカーオリジナルであるというのが特徴のパソコンになります。
完成品を販売しているので、スペックが決まっておりある程度妥協しなければならないこともあります。妥協して購入してみたらストレージの容量が足りず動画編集で使いにくかった、快適に動いてくれないなど、後悔することもあります。
また、自身には不要な機能が搭載されていることもあるので、その点がムダだと感じるかもしれません。
自作のパソコン
パソコンを構成するCPUやメモリ、ハードディスク、マザーボード、筐体など、一から自身で選んで個別に購入し組み立てたパソコンです。すでに完成しているメーカー製パソコンとは違い、自身好みにカスタマイズできるだけでなく、コストも安く抑えることもできます。
ただ、パソコンを自作するにはそのための知識が必要で、知識がなければちゃんと使えるパソコンを完成させることは難しいでしょう。
ショップ系のパソコン
自作パソコンは自由にパーツを選ぶことができコストを抑えられますが、そのパーツを選ぶ段階で間違ってしまうと接続できなかったり、性能を最大限に発揮することができないこともあります。
ありがちな間違いは同じ規格のパーツではないというケースですが、規格が合っていても相性が悪く思ったような性能にはならなかったということもあります。自作パソコンはコストを抑えることが可能なのに、パーツを選び直すようなことになって結局高くついた、ということもあります。
ショップ系のパソコンの場合は、自作パソコンと同じようにパーツを選んで組み立てていくものですが、パーツを選び組み立てる人はパソコンに精通したプロであることから、自作パソコンにありがちな失敗がありません。
ショップ系のパソコンなら希望する性能を持つパソコンを、価格を抑えて購入することができるため、メーカー製のパソコンよりもコストパフォーマンスが優れているうえに、自作パソコンよりも心置きなく使用することができます。
ただし、ショップ系のパソコンも注意しなければならない点があります。それはショップによって使用するパーツのメーカーが、公開されていないこともあるからです。
どこのメーカーのパーツなのか明らかにされていないのは不安なうえ、そのショップ自体を信頼できるのか疑わしくなるかもしれません。そのため、ショップ系パソコンを購入する際は、使用しているパーツのメーカーなどを公開しているかどうか、チェックするようにしましょう。
BTOパソコン
BTOパソコンは、ひとつの販売形態ではなく、メーカー製のパソコンとショップ系のパソコンにおいて販売形態の一部として取り扱うものです。自作パソコンにように自由にパーツを選ぶのではなく、メーカーやショップが用意したパーツのなかから、選択することになります。
自身で選べないということを不満に思う人もいるかもしれませんが、組み合わせて使えないようなパーツは含まれていませんから、相性が悪くて失敗するといったこともほとんどありません。
自身の用途に合わせてパーツを選ぶという自作パソコンのような特徴があり、なおかつ問題が発生することがない完成品として手に入れることができるのは、BTOパソコンのよいところだといえます。
主に動画編集をしたいので大容量のストレージが必要、多少予算をオーバーしても高性能なCPUで快適にパソコンを使用したいなど、カスタマイズして自身のわがままも叶えてくれます。
BTOパソコンのメリット・デメリット
BTOパソコンにはどのようなメリット・デメリットがあるのか解説します。
メリットその1・自身にぴったりのパソコンが手に入る
まず第一に、自身にぴったりのパソコンを購入できることがあげられます。市販されているメーカー製のパソコンの場合は、特定の人向けというよりも多くの人が使えるように標準的なニーズに合わせて製造されています。
そのようなパソコンは、無難に使えるという点で初心者やパソコンの使用頻度が高くない人なら問題ないのですが、より高い機能を必要としたり自身にとってムダな機能は省いてその分コストを抑えたいという人なら、市販品では満足できないかもしれません。
メーカー製のパソコンと同様に、ショップ系のパソコンも不特定多数のユーザー向けにつくられたものなら、やはり自身の求めているパソコンとは違うと感じる可能性もあります。
BTOパソコンなら必要なものは必ず取り入れることができ、不要なものは外すことができる、自身だけの特注パソコンを手に入れることができます。
メリットその2・パーツや組立に間違いがない
パーツの選択を間違ったり、組み立てを失敗してしまうという問題がありません。自作のパソコンは、自身で好きなようにパーツを選ぶことができりますが、規格が合わないことに気がつかずパーツを購入してしまうこともあります。もちろん、規格が違うため接続することはできません。
また、規格は合っていて問題なく接続できたとしても、うまく作動せずその原因もよくわからないことがあります。パソコンのパーツにも相性があり、相性が悪ければ思ったようには動作してくれません。
そんな相性問題は、知識と経験が豊富な人でも起こりうることで、実際に組み立て動かしてみて失敗したとがっかりしてしまうこともあります。パソコンを自作する場合によくあることに、組み立ての際に無理をしてパーツを傷つけてしまったり、ケーブルの結線がうまく収まらず冷却風が通るのを邪魔してしまうというトラブルも起こります。
BTOパソコンなら、長年の経験と知識、技術を持つメーカーや専門のパソコンショップが、間違いない組み合わせでパーツを選び、間違いなく組み立てを行うので、パーツ選びに失敗することがありません。
メリットその3・コストを抑えることができる
必要なパーツのみ選び、不要なパーツは除いたり性能を低く抑えることができるので、ムダを省きコストを抑えることができます。それにより、必要なスペックを満たした市販のパソコンを購入するよりも、安く購入することができます。
また、BTOパソコンはパーツをまとめて購入するので、個別に購入する自作パソコンよりも合計金額が安くなる場合もあります。
メリットその4・あとで部品交換も可能
自作のパソコンの場合、完成した後でもドライブを追加するなど部品の追加・交換が可能です。BTOパソコンでショップ系では、統一規格による汎用性の高いパーツを組み合わせているためカスタマイズが可能です。
交換が可能で、パーツが古くなれば新しいものに取り換えて、長期間使い続けることもできます。
メリットその5・ムダなものが入らない
市販されているメーカー製のパソコンは、すでにさまざまなソフトがインストールされているものが多いです。超初心者向けのパソコンガイドや、子ども向けのパソコン入門ソフトなど、不要なものや使わないものが多く、うんざりした経験がある人もいます。
もちろん中には役立つソフトもあるかもしれませんが、ほとんど使わないようなソフトのせいで動作が重くなってしまったり、HDD/SSDの容量を取られしまったりすることがあります。
BTOパソコンなら、そのような不要なソフトはインストールされず、必要なソフトを選んで入れることができるのでムダがありません。
デメリットその1・現物を確認することができない
すべてのBTOパソコンが該当するわけではありませんが、BTOパソコンはインターネット注文が一般的であり、現物を見てどのような商品なのか確認することができないことが多いです。
サイズや重要が掲載されていても、実際に見て確かめると違うということもあります。
デメリットその2・パソコンの知識はある程度必要
パーツ選択をおまかせするのではなく、自身で選択できるという自由があるBTOパソコンですが、どのパーツにするかを自身で決めなければならないということでもあるわけです。そのためパソコンについてまったく知識がない人なら、BTOパソコンの購入は難しいでしょう。
自身の用途に合わせるにはパーツのグレードはどの程度が適しているのか、それを見極めることができないと性能が不足することもあり、コストをかけ過ぎてしまうこともあります。
デメリットその3・特殊な製品はない
汎用性を重視しているBTOパソコンそのため、独自の機能や形状が採用されたような特殊な製品はありません。
メーカー製のパソコンには、液晶モニターと本体とが一体になったものや、指紋認証センサーが内蔵されたものなどがあり、オリジナルのパーツを数多く使用した独自の製品が販売されています。
しかし、BTOパソコンでは独自の形状・機能を持つものは望めませんが、工夫すれば同じような使い勝手を実現することはできます。たとえば、液晶モニターに超コンパクトである筐体を組み合わせたり、指紋認証センサーも外付けすれば問題ありません。
デメリットその4・レビューや口コミを参考にできない
市販されているパソコンなら、購入した人たちのレビューや口コミをインターネットで探しチェックすることができます。
しかしBTOパソコンの場合は受注生産であり、まったく同じものを購入して使っている人を見つけることが難しいです。まったく同じパソコンを見つけることは難しいのですが、筐体やキーボード・マウスの使い勝手などは、シリーズやブランドで名前を検索して知ることが可能です。
デメリットその5・納品に時間がかかる場合がある
BTOパソコンは受注生産、注文する際に購入者がパーツを選ぶところから始め、組み立てがスタートするため市販品を購入するようにすぐに手に入るわけではありません。メーカーやショップで多くの注文を受けている時期なら、普段よりも納品までの時間がかかることもあります。
だいたいこのくらいの時期に納品できるだろうと考えていても、場合によっては遅れてしまうこともあるので、購入することが決まった段階で早めに構成を決定して購入するのがおすすめです。
また、BTOパソコンには急ぎの場合に便利な即納モデルも用意されていることがあります。すでに組み立ててある完成品ということで、価格が安い傾向がありそれが自身に合ったモデルならお得に購入できます。
BTOパソコンのおすすめのカスタマイズポイントとは?
BTOパソコンは、手軽にカスタムできるという特徴があります。おすすめのカスタマイズポイントについて説明します。
動画編集をしたいなら
動画編集をしようとすでに自宅にあるパソコンでやってみたらどうもうまくいかない、そんな不満を感じた人も多いのではないでしょうか。動画ファイルはサイズがとても大きいので、大容量のストレージが必要です。
動画編集をストレスなく行いたい人なら、大容量HDDを選択してください。動画編集では、編集する動画の長さや解像度にもよりますが最低1TBあればOKといわれています。大量で長時間、あるいは4Kの動画編集を行いたいなら、HDDは最低4TBがおすすめです。
また、快適に編集するためにはメモリ容量も要チェックです。目安としてはフルハイビジョン編集であれば最低でも8GB、4Kの編集なら最低でも16GB以上は欲しいところです。作成した動画をBDに記録したいなら、BD-R/REドライブを選択しましょう。
快適にゲームをしたい人なら
ゲームによって推奨メモリが大きいものがあり、そのようなゲームでストレスなく快適に遊ぶにはメモリは最低16GBを選んでください。遊ぶのは2Dゲームのみなら、オンボードグラフィックのみのモデルがおすすめですが、処理が重いと感じることがあるかもしれません。
そのような場合に備えて、グラフィックボードを追加できるモデルを選ぶのがおすすめです。3Dゲームで遊ぶということなら、高速なグラフィックボードを搭載しなければならないでしょう。メーカー、型番で迷うかもしれませんが、どれが一番とは一概にいえません。
選ぶときに実際の型番も含め検索して価格差・パフォーマンスの違いをチェックし検討してみてください。
いわゆる「光り物」のゲーミングデバイスの追加を希望するなら、PCのケースはRGBファン搭載で、ディスプレイ用LEDライティングアイテム、マザーボードのRGBLEDファンなど、追加して楽しむこともできます。
ネット配信したい人なら
今は誰でも気軽にYouTubeなどでネット配信していますが、リアルタイム配信なら特別に高い性能がなくても問題なく行うことができます。カメラで撮影した動画をそのまま実況配信するので、一般的なパソコンでも十分でしょう。
ただ、無線LAN(Wi-Fi)で接続したい場合は、高速規格である「IEEE802.11ac」搭載モデルを選ぶのがおすすめです。ゲームの実況配信を行いたい場合は、配信とゲームプレイを同時に行うだけのスペックが必要、複数のディスプレイ端子が搭載されたモデルを選んでください。
編集後に配信するなら、動画編集のためのスペックも必要です。動画のエンコードを早めに終わらせたい場合は、CPUは高速なものを選択してください。筐体にも凝りたい、派手に見せたいという希望があるなら、フロントファンにLEDを搭載したものがおすすめです。
ビジネスで使用したい人なら
遊びや趣味ではなく、ビジネスで書類作成やWebの調べ物程度の使用の場合、それほど高性能なパーツを選ばなくても問題ありません。そちらにかからないぶん、お金をかけるとしたら、Windowsやアプリの起動を高速化し静音性が高いSSDがおすすめです。SSDはHDDの代わりに選択します。
また、Wi-Fi(無線LAN)も便利に使えるので、接続したいなら内蔵Wi-Fi機能を選んでみてください。ビジネスといえばオフィスソフトが必要になりますが、オフィスだけでなく互換ソフトを選ぶこともできます。
オフィス互換ソフトなら、価格を抑えることができます。エクセルで大きな表を扱ったり、Webブラウザで情報を検索しつつWordで文章を書くような場合には、複数のモニターを接続して使うマルチモニターがあると便利です。
マルチモニターがあれば、作業効率の大幅アップが期待できます。マルチモニターを利用したいなら、マザーボードに複数の映像出力端子を備えてあるモデルを選びましょう。
写真の加工や現像をしたい人なら
写真を加工や現像の処理は、CPUがより高速であることで処理能力がアップし。快適にすばやく終了させることができます。細かく修正するような作業が多くなる可能性があるのなら、CPUは高速なものを用意したほうがよいでしょう。
3Dゲームに適しているような高度なグラフィックス性能は必要ないのですが、グラフィックチップ(GPU)の機能を利用できるソフト使用するなら、グラフィックボードを追加するのがおすすめです。
一眼レフやデジカメなど、高解像度の写真を複数同時に加工したいなら、最低でも16GBのメモリを選択しましょう。RAW画像の現像を行うことが多いなら、大容量ファイルを読み書きすることになるため、高速ストレージであるSSDを選択しましょう。
パソコンの動作音が気になる人なら
パソコンの動作音は、気になる人なら気になってしまうものです。また、自室ではなく家族が揃うリビングなどにパソコンを設置している場合も、音が気になってトラブルになるケースもあるため、騒音が気にならないタイプのパソコンを選んだほうがよいでしょう。
たとえば、音が気になる部分である冷却のためのファンは、低い回転数でも効果的に働く大口径のものを選ぶと、騒音の発生を抑えてくれます。頻繁にゲームをするなら別ですが、そうでなければファンが騒音源になるグラフィックボードを選ばず、内蔵グラフィック機能を選んでみてください。
さらに、大容量ストレージが不要ならHDDではなくSSDの方を選ぶようにしましょう。静音化したいのであれば、静音対応のCPUクーラーというものもあります。
CPUの発熱が気になる人なら
パソコンを使用していると熱が発生するのは当然ですが、時折許容範囲を超えた熱を発生することもあります。パソコンのどの部分が熱を持ちやすいかというと、パソコンの頭脳であるCPUです。
多くの処理を行うことで熱を持ちやすくなっており、パソコンに負荷がかかるような使い方をすることで、必要以上に発熱してしまいます。CPU自体は高温に耐えられる構造で、高温で発熱したからといって壊れてしまうことはありません。
周辺のパーツやパソコン本体は高温でダメージを受けてしまう可能性があるので、CPUが過剰に発熱するのを防ぐことが大切です。CPUの発熱を抑えるための対策として、CPUクーラーというパーツが搭載されます。
CPUクーラーには冷却ファンの空冷式と、冷却液を使用した水冷式があります。より冷却効果が高いのは水冷式で、空冷式では放熱された熱がケースの内部に対流してから排気されるのに対し、水冷式では熱が効率的にケースの外部へと排気されます。
また、水冷式はコンパクトにまとめることができ、ケースの内部に余裕ができます。
家庭用ゲーム機の画面を配信したい人なら
家庭用ゲーム機の画面を、パソコンで録画・配信したいならキャプチャーボードを選択するのがおすすめです。外部から映像信号や音声信号を取り込んで、動画データに変換して保存するという装置になりますが、家庭用のゲーム機につなぐと画面録画機能がないゲーム機でも画面の録画を行うことが可能です。
HDMIパススルーに対応している機種なら、パソコンに大きな負荷をかけずに録画することができます。配信サイトによっては、家庭用ゲーム機のシェア機能でサポートされていない場合もありますが、キャプチャーボードがあればパソコンで生配信が可能です。
パソコンで配信するため、ゲーム機のシェア機能のように配信時間の制限はないので、制限時間を気にせず録画することができるようになります。
また、キャプチャーボードがあればパソコンで直接録画できるので、ゲーム機で録画した動画のデータを、そこからパソコンへ移す作業も不要です。
まとめ
BTOパソコンとは受注生産のパソコンで、自由度が高くしかもコスパに優れており、自身の用途に合わせたぴったりのパソコンを手に入れることができます。完成した状態で店頭に並ぶような、メーカーやショップが製造したパソコンでは物足りない、自身に合うものが見つけられないなら、BTOパソコンを検討してみてください。購入にはパソコンの知識が多少必要になりますが、本当に欲しいパソコンをリーズナブルな価格で手に入れるには、BTOパソコンがおすすめです。